
転機となった関東大震災
水島あやめが関東大震災に遭ったのは、日本女子大学三年の秋で、二十一歳のとき。大学にも池袋駅にも近いところに家を借り、母とふたりで住んでいた。
その年に、被災したときの様子を母校の同窓会報に寄せている。
少女時代から小説家にる夢を抱き、大学に入ってからも創作に打ち込み、雑誌「面白倶楽部」の懸賞で当選。同誌上に作品が掲載され、小説家への足がかりを掴んでいた。そんなあやめが、映画のシナリオライターの道に方向を転じる契機になった出来事だった。
『 あの日を追想して幾度も繰り返す事ながら、ほんとうに夢にも思い掛けなかった此の度の災禍、誠に誠に驚かせれて了いました。御在京だった同窓のお方のうちには、罹災遊ばした方々もよほどお有りの事とお察し致しますが、そうした皆様に誌上で失礼ながら、深く深く御同情申し上げます。
私は在京して居りましたけれども、運よく市外でございましたので、地震で恐ろしい思いをしましただけで、幸い火事は免れる事が出来、どうやら今日まで無事に過ごして参りました。
あの時の感想--と申されましても、今になって考えて見ますと、何が何やら、まるで夢の中の出来事の様で、ちっともまとまりが附かないのでございます。しかし、此の千古未曾有の災害を直接に経験した一人として、あの時の有様を申し上げるのも、あながち無駄というばかりでもないかと存じますので、お言葉に甘えまして、あの際の経験を少しばかり申し上げることに致します。
今になって、静かに考えてみますに、あの大災の為に、一番強く深く感じさせられました事は、自然力の偉大さと信仰というものの強さ、そして、私共が常々云ったり書いたりして居る思想とか人生観とかいうものが、あまりにも虫のよいひとりよがりの理屈に過ぎなかったという事でした。私共の平生考えていた人間というものと、此の度の災害時に現れた人間と、そこに非常の差異のあった事が、私は実にハッキリと知り得る事が出来たのでございます。
--九月一日--
その日はほんとに蒸し暑い厭な日和でございました。丁度お昼の仕度に台所へ下りた私が、襷をかけ終わったと思う瞬間、グッッと家がゆすれました。
「あ、地震--」と云ったきり、まだ何か云おうと思って居た私は、忽ち起こった次の大震動に、思わずハッと息をのんで了いました。私はすぐ六畳へかけ込みました。丁度二階に上がろうとして居た母は、黙ったまませわしく私を引張って、二人は梯子段の下に身をひそめたのです。
その時、家はズシンという物凄い音と共にたしかに上へ持ち上げられました。アッと思う暇もなく続いて起こる波の様な水平動は小さな家を船の様にゆすりました。
ギーギーと悲しげに鳴る梯子段に取りすがったまま、二人はぢっと動かずに居りました。そして、喰い込むように見つめて居た鴨居が抜けて落ちた時、ああもう駄目だと思いました。
その時、耳には何も聞こえませんでした。目も無意識に梁のあたりを見つめたまま、私はただ大声に救いを神に祈りました。母はもう一心不乱に、生まれ故郷の鎮守様を祈りました。ああその祈り、生死の境にヒシと身を寄せ合ったまま、母子が振り絞るその悲痛の祈りの声こそ、私共の生涯に於て、二度と叫ばれない真剣なものだったろうと思います。
げに神を信じる強さ。こうした場合、人は必ず何者かの絶大な力を頼らなければ居られないという事を、私はしみじみと感じました。
又一ゆり、又二ゆり、震動は寸時も止まず、二人の襟元には、壁土が雨の様に降り注ぎました。
「もう駄目だ--」母はあえぐ様な声で、遂に最後の言葉をもらしました。
--私は、今死ぬのか知ら--と思った時、私の頭は茫と空になって了いました。経て来た二十年の生涯は、煙の様にスーと消えて了いました。『死』という事実に対した時、多くの人は我が生涯が絵巻物の様に心をかすめるという。しかし、私は何も浮かんで来ませんでした。歓喜もなく悔恨もなく、又生に対する執着もなく、まるで夢を見て居る様な気持ちで、眼前に迫った死に対したのです。
若しもあの時家が潰れたなら、私はあのボーとした気持ちで、何も思わずに死んで了ったに違いありません。
ほんとに私は、二十年の月日を空に過ごしたのであったか、と後で思った時、実に淋しい気持ちが致しました。喜びもなく悲しみもないという事は、一面平和に安らかにも思われますけれども、一面非常な淋しい事でございました。あの時、死んで了ったのなら、今頃どうなって居るだろう等と、後で時々思い出しましたが、幸いにも死なずに逃げ出す事が出来たのです。
時間にしたら何分位後か、やっと淋(激)しい震動が静まりましたので、母も私も、ホット息をついて顔を見合わせました。漸く梯子の下から出て見ますと、座敷一面壁と土との大狼藉で、障子は裂け襖は破れ、実にひどい有様でございました。しかし、もうそんな物を構って居る暇はない、二人は手に一物も持たず、上草履のままで、すぐに戸外に飛び出したのでした。家の門を出ますと、すぐ墓地がありますので、そこまで一散に走りつけますと、そこの空地には、もう近所の人々がすっかり集まって居りました。見れば、誰も彼もはだしで、その顔には、血の気がありませんでした。四辺を顧みれば、有りとあらゆる墓石は、一つ残らず地に転げ落ち、その荒涼とした有様の無惨さ、実に寂しさの極みでした。
そのうち、ドゞ‥‥という、恐ろしい地鳴りと共に、激しい揺り返しが参りました。立って居た私共は、危うく投げ倒され様として、思わず地面にしゃがんで了いました。しかし、その地面とて、何処がパクッと割れないとも限らない、その波のように動く地上にしがみついて、一たまりも無さそうに揺れ傾く我が家を見つめて居る心の不安さ、その時の気持ちは何と云って現していいものやら、自分ながら今になっては分からぬ位でございます。私は生きたいとは思いませんでした。しかし、揺れる度に感じる恐ろしさと不安さとは、やっぱり心の底に、生きたいという強い願いがあった証拠だと思います。が、これは後で考えた事、その時には、生命を助かりたいとはちっとも思いませんでしたが、ただ目前の恐ろしい震動が早く止んでくれればいいと、それのみ一心に願って居たのです。今になって考えますと、何だか矛盾した心持ちの様に思われますけれど、その時には全く死だの生だのという事は念頭になかったのです。
ただ恐ろしかった、自然の力が実に恐ろしかった。今でこそ可笑しい位、また実際に会わなかった人々には、情けない程小膽だと笑われもしましょうが、あの時の気持ちこそ、決して他の想像の及ぶものではありません。こうして終わって了った後でこそ、ただ大地震があった位ですみましたが、あの時の心では、天地一切、次の瞬間に砕け散って了うのではあるまいかとさえ思われました。(中略)
こうして第一日は暮れました。半天を染むる紅の煙を眺めながら、震える大地で侘しい夢を結んだその夜の事は、永久に忘れる事は出来ないだろうと思います。
二日の日も、終日震動に胸を轟かせて、そして夜はやっぱり野宿しました。
此の二晩の野宿で、私共はずいぶん身体に苦痛も被りましたけれども、平生あまり語り合った事も無い様な人々とまで、まるで十年の知己の様に親しみ合って、常には現れて居ない、美しい人間の心を見出したという喜びは、実に得がたい賜でございました。
こうして、此の度の震災では、随分害も受けました。しかし、又その為に益した事も、どんなに多かったかしれません。
自然力と人間の科学力との戦いも試されました。信仰の問題も与えられました。その他の思想や人生観も、得がたい試練に会う事が出来ました。
生死の境に立って見るという事、それはほんとに尊い経験でございました。その為に、犠牲になった方々は、何と申し上げ様もないお気の毒さでございますけれども、こうして大なる犠牲を払って得た此の度の機会こそ生き残った私共が、あくまで感謝しよりよく活かしていかなければならないものだと存じます。
まとまりもない事を、随分長々しく申し上げました。しかしあの地震によって感じました事は、全く此の様に断片的であったという事を察して頂いて、お許しをお願いする外はございません。
焦土にも秋は来ました。勇ましい金鎚の響きは、蒼く晴れた空にこだまして居ります。その隆々たる帝都復興の意気を喜びつつ----ではこれで失礼して●を擱きます。』(長岡高等女学校同窓会報 大正九年版)
………2012年4月6日公開

二十世紀の女性史と水島あやめの生涯
水島あやめは、映画脚本家としては、わが国で最初の女性であった。そして、大衆文芸の世界においても、少女小説の作家として活躍した。封切られた映画の本数も、刊行された小説の冊数も多く、第一線で活躍した期間も長い。いずれの分野においても、当時において人気の作家だったことは確かである。にもかかわらず、〔水島あやめ〕という名前は、今日に至るまで、さほど注目され取り上げられることはなかった。
これには、次のような理由が考えられる。
まず、あやめが脚本家として活躍した時代の映画はサイレント(無声映画)であり、今日の映画やテレビドラマのシナリオとは、まったく別のものであったことが上げられる。映画のシナリオそれ自体が作品として確立され評価されるようになったのは、トーキー(有声映画)時代になってからといえる。サイレントとトーキーでは、シナリオの手法において大きな違いがある。サイレント時代の映画は、監督は評価されても脚本家が評価されることは、まずなかった。野田高梧や北村小松など、あやめと同時代の脚本家が今日高い評価を得ているのは、トーキーの時代になり、いい作品を書いた実績から遡って評価されているようである。残念なことに、あやめのトーキー作品は、松竹を退社する年に公開された一作(『輝け少年日本』)だけで、フィルムも残っていない。また、あやめの得意とした「母もの」は、映画以前の新派劇の流れを汲んでおり、当時の女性たちに受けがよく興行的価値は高かったものの、芸術的価値としては評価が低かったのも事実である。橋田寿賀子氏が、女性脚本家の先駆者として地位を確立するのは、戦後の映画第二期黄金時代を経て、テレビ時代が到来してからのことである。
つぎに、少女小説についてであるが、これも文学的評価の基準が障壁になったと思われる。成人向けの大衆小説は、菊池寛、直木三十五、吉川英治らの作品によって、文学的評価と地位を確かなものにした。しかし、少女小説は、『少女倶楽部』や『少女の友』などの雑誌に掲載され、全国の少女たちの間で爆発的に読まれたにもかかわらず、文学者や文芸評論家からは、センチメンタリズムに満ちた低俗な読み物と酷評されつづけ、今日に至っている。少女小説の代表作といえば、吉屋信子の『花物語』が想起されるが、この作品が誉れを得るようになったのも、彼女が成人向けの大衆小説や歴史小説で、数多くの秀作を著したからであろう。川端康成も、昭和初期に少女小説を書いていたことは有名であるが、それも少女小説それ自体が名作と評価されているわけではなく、のちに純文学作家として大成した康成の過渡期の創作ということで取り上げられていると思われる。あやめは、昭和十二年に年間十二巻発行された『少女倶楽部』に二十回(連載と読み切りの短編を合せて)も作品が採用され、また昭和二十四年には年間七冊の単行本が刊行されている。小説家として、それほどの人気を博してもなお、実績を評価されないのは、やはり少女小説作家だったからにちがいない。
映画史におけるサイレント時代の脚本と、文学的価値のおける少女小説の評価や位置づけを、このように整理するならば、水島あやめの評価がそれに準じるものであっても仕方ないといえる。
しかし、視座をかえ角度をかえて、あやめの生涯と業績を見直すと、まったくちがった評価が浮かび上がってくる。それは、女性史という視点である。
二十世紀は、女性の人権獲得の世紀であった。近代の女性史を概観すると、樋口一葉が文壇に登場し、ついで与謝野晶子が「君死にたまふことなかれ」を発表する。その後平塚らいてうが「原始、女性は太陽であった」と発信したことが契機になって雑誌『青鞜』が創刊される。高等教育を受けた若きインテリ女性が『青鞜』に集い、女性の意識啓蒙に取り組み、人権獲得を叫びはじめる。やがて女性参政権運動をはじめとする解放運動が各分野で活発となり、戦う女性が登場し、女性の人権と権利が法的に獲得されていく。そして、近年に至っては、男女雇用機会均等法の制定や男女共同参画社会への取り組みなど、真の男女平等というゴールに手の届くところまで、女性の立場は回復し確立されてきている。しかし、こうした歴史は裏側から見るならば、とりもなおさず大半の女性が、長い年月を、古い価値観と境遇のなかで、虐げられ苦労していたことを意味している。
こうした思想や社会運動が牽引してきた表の女性解放や人権獲得の運動を、底辺で支えていたのが映画であり、大衆文芸だったのではないかと考えられる。なぜなら、運動に積極的に参加する女性より、映画や大衆文芸などに親しみながら生きていた女性の方が、はるかに多かったからである。
工業の発展に伴い都市化が進み、人々には経済的な余裕が生まれてくる。女性の働く職場も増え、生き生きとした女性が住む都会は華やかさで満ちてくる。そんな女性たちが描かれる映画は、都会に暮らす女性たちにとっては心躍らせるものであり、地方に住む女性たちには夢やあこがれの対象となった。とはいえ、大正デモクラシーと、それにつづく昭和モダニズムの自由な世相にあっても、女性たちはまだ十分に解放されていたわけではなく、家のしがらみや女性蔑視、社会的な差別など、さまざまな古い因習に束縛され、つらく不自由な事情を抱えていた。しかし、映画や大衆小説は、たとえ一時ではあっても現実を忘れさせ、夢の世界に誘い、心を解放させてくれる。そうして癒された女性たちは、ふたたび現実に戻って、これまでどおりの日常を耐えつつ送る。そんな女性たちにとって、映画は心のオアシスであり、これまで知らなかった世界を教え、夢見させてくれる貴重な存在であった。
大衆文芸もまた、同様の役割を果たしていたのにちがいない。だからこそ、多くの観客が映画館に足を運び、様々な大衆雑誌が爆発的に読まれたのだろう。そして、こうした現象は、少女たちの世界においても当てはまっていたものと思われる。
脚本家として、「母もの」と「少女悲劇」などの「お涙頂戴もの」を得意としたあやめは、女性にとって「泣く」こと、涙を流すことの意味を知っていた。登場人物に共感し同情するから涙が流れる。それが心を解放し慰めてくれる。それが「泣く」ことの効用であり、そこに「お涙頂戴もの」の意義があるという趣旨のことを書き残している。
あやめは新潟県の寒村と小都市で少女時代・思春期を過ごし、上京して大学に進んでからは、大都市東京において映画と大衆文芸という華やかな世界で生きた。豊かな感性を備えていたあやめは、さまざまな女性の姿を見ては感じ、考え思いをめぐらせたことだろう。それを作品のなかに表現し、全国の女性や少女たちへ発信していった。たしかに、あやめが脚本を書いた映画は、声もなく(弁士はいた)、音楽もなく(楽団の演奏はついてはいた)、色も白黒の初期の映画で、まだまだ開発途上の「見せ物」だったかもしれない。また、あやめが書きつづけた少女小説は、センチメンタリズムに満ちた児童文学以前の「低俗な読みもの」だったかもしれない。しかし、そんなあやめの作品は、近代日本の女性の置かれていた状況と心の内面に照らし合わせてみたとき、おおきな役割を果たしていたことがわかる。
一九○三(明治三十六)年に生まれ、一九九○(平成二)年に生涯を終えたあやめは、この女性の解放と人権獲得の二十世紀を、おおむね通して生き抜いた。そして、八十七年の生涯をつうじて、数々の夢を実現していった。
自己表現できる職業について活躍したこと。男性社会にあって経済的に自立したこと。全国の女性と少女に夢とあこがれを贈りつづけたこと。病気の母を最後まで介護しつづけたこと。そして、自分の貯蓄で有料老人ホームに入居して晩年を過ごし、生涯を閉じている。ただ、一度結婚したものの四年後に離婚。家庭をきずき、子どもを持つことは叶わなかった。それは、母の介護との両立の問題だったと想像される。
水島あやめの生涯と業績は、こうした女性史の観点からとらえ直してみるべきではないだろうか。思想や運動は集団で取り組まれることによって顕在化し、社会的に認知される。しかし、思想や運動は、一人ひとりの生き方に浸透していってはじめて、実を結んだことになるのだろう。差別からの解放と人権の獲得のその先には、社会的自立と自己責任という次の段階が待っている。あやめの歩んだ生涯は、女性の自立と自己実現の一つのモデルといえるのかもしれない。(平成二十一年七月某日)………2012年3月24日公開

ペンネーム「水島あやめ」は、こうして決まった。
「水島あやめ」というペンネームが決まったのは、脚本家としてのデビュー作「落葉の唄」が完成間近に迫った頃。日本女子大学4年生の秋だった。
晩年になって、知人宛の手紙にこう書いている。
『私のペンネームは、小笠原プロで、初めて作品が出来たとき、本名だと、学校を退校もなるかもしれないので(そのころの目白は、きびしくて、沢村貞子さんなど、ちょっと新劇に出て退校になった)ペンネームをつけることにし、丁度、小笠原さんの広い裏庭の池に、花しょうぶが盛りだったので、わたしはその花が好きだったし、名前を『あやめ』にして、それに似合う『水島』を姓にしたのです。』
あわただしく考えられたこのペンネームが日本の映画史に残ることになろうとは、この時の千年には思いも寄らなかったことだろう。

わが国で最初の女性脚本家、水島あやめ
大正13年11月22日、水島あやめの脚本家デビュー作『落葉の唄』は、浅草遊園第二館で公開された。
それに先立ち、『活動雑誌』が大正13年10月号で、「最初と最後のシーンは悲痛な気分があって落葉が雨と降る下に、可憐な妹娘が淋しく葉を拾って集めているのは哀愁の気がした。事件に従って段々と淋しくなって行く趣きもかなりでていた」(吉山旭光評)という紹介文を掲載。そして、公開後には『キネマ旬報』(大正13年12月号)が、「あわれな少女小説、少女詩だ。淡いセンチメンタルが、この映画の凡てだ」(佐藤雪夫評)という辛口の批評を載せる。
映画の出来映えは、よくなかったのかもしれない。しかし、たとえ完成度は低かろうと、劇場で公開されたうえで、映画専門雑誌上で専門家の批評を受けていることの意味は大きい。この記録が、水島あやめがわが国で最初の女性シナリオライターであることを示している。
というのも、この時期、もうひとりの女性が、脚本家としてデビューすべく準備していた。日活の林義子である。彼女の最初の作品『慕い行く影』前編(日活京都第一部)が公開されたのは、大正14年2月28日。あやめの『落葉の唄』公開から、わずか3ヶ月のちのことであった。その後、林は日活と千恵プロで活躍し、19作品(原作9本、脚本10本)が映画化されている。
こうして、奇しくも日本の映画界をリードしていた松竹蒲田と日活から、水島あやめと林義子というふたりの女性脚本家が相前後してデビュー。昭和初期の第一期黄金時代を舞台に活躍することになる。

『水兵の母』に海軍が全面協力した背景
『水兵の母』の撮影には、海軍省が軍艦橋立をはじめ数隻の軍艦、それに水兵や海軍の施設などを提供。さらには、ロケも小笠原諸島で行なうなど、全面的な協力をおこなっている。
これだけの支援を得られるようになったのには背景がある。
小笠原映画研修所所長で、この映画を監督した小笠原明峰の父長生(ながなり)は九州唐津藩主小笠原家の血筋で、このとき海軍中将であった。日清戦争のとき、軍艦高千穂に乗り組み黄海海戦等に参戦した長生は、戦後になってこの時の体験を『海戦日録』にまとめ、高い評価を受ける。「水兵の母」は、このなかのエピソードのひとつであった。この挿話は国定教科書に採用され、太平洋戦争が終わるまで人気の教材となる。
長生は、海軍において要職を歴任し、その過程で多くの人物と出会っている。軍令部参謀時代には、日露戦争時の海軍司令長官東郷平八郎と知り合い、明治44年には学習院御用係となって、院長乃木希典大将のもとで役を務める。同45年(大正元)の明治天皇崩御のときには、乃木大将夫妻が殉死する直前まで乃木と深く関わり、遺書や多数の遺品とともに後事を託されている。さらに大正3年には、東宮御学問所の設置にあたって総裁東郷平八郎の推薦で幹事に迎えられ、以後七年間、皇太子すなわち若き日の昭和天皇の教育にあたった。
ちなみに、長生の次男長英(明峰の弟)もまた、皇室と深い交流があった。
長英は、秩父宮の学習院幼稚園からの学友であった。彼は明峰とともに小笠原映画研究所を立ち上げ、三善英芳という名で監督をしたあと、小笠原章二郎という芸名の俳優に転じた。しかし、父長生はこれを嫌って、長英を勘当してしまう。進退きわまった彼を見て、秩父宮が長生にとりなしてあげている。長英がお礼を申し上げると、「ひとつ、お前の後援会を作ってやろう」とまで言われた。さすがに長英は、畏れ多いことと辞退している。(『資料高松豊次郎と小笠原明峰の業績』)
このような長生親子の経歴や人脈などから、小笠原家がいかに名門の家柄であるか知ることができる。そして、それゆえに、明峰は海軍省の強い後押しを得ることができたのであろう。

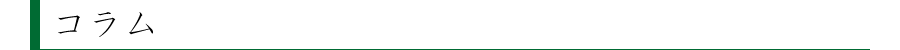
関東大震災と映画
大地震は、東京を瓦礫の山と焼け野原にした。信じがたいほどの数の生命を奪い、また、かろうじて助かった人々にも深い傷を残した。廃虚の街は、容易に立ち直れないと思われた。
しかし、打ちひしがれている人々ばかりではなかったようだ。あやめ自身が書いているように、秋にはもう、「勇ましい金鎚の響きは、蒼く晴れた空にこだまして」いた。
なかでも、映画業界の動きは早かった。
銀幕から語りかける端正な顔だちの男優…。綺麗に着飾った美人女優が微笑みかえす…。滑稽に立ち振る舞い、笑いを誘う喜劇俳優…。俊敏に立ち回り、悪をたたっ切る凛々しい剣客…。
笑いと涙をさそい、夢と希望と憧れを届ける映画は、奈落の底で苦しむ人々に、たとえ小一時間ではあっても、つらくきびしい現実を忘れさせてくれた。傷ついた心をいやし、苦境から立ち直る活力を与えていたのである。
劇場に群がる人だかり…。入場を待ちわびる楽しげな顔…。満足に顔を輝かせて、劇場をあとにする人々…。笑顔の子どもたち、女性たち…。
映画館を取り巻くいきいきとした人々の姿に、あやめもまた、映画のもつ力に深い感銘を受けていた。 ………2012年4月14日公開