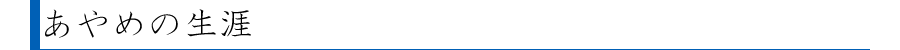大正13年(1924)〔21歳〕

大学4年の春、小笠原映画研究所(のちの小笠原プロダクション)で、映画シナリオを学びはじめる。
夏頃、小笠原長生原作の『水兵の母』を、千年の脚本で映画化することに決まる。
11月22日、千年が脚本した『落葉の唄』(原作国本輝堂・監督小笠原明峰)が、浅草遊園二館で公開。『キネマ旬報』『活動雑誌』などに紹介される。これが、女性脚本家によるわが国で最初の映画作品となった。
公開を前に、ペンネームを<水島あやめ>とする。(以降、あやめと記す)
この年、写真物語「街の曲」が雑誌『少女倶楽部』に掲載され、はじめての原稿料をもらう。
大正14年(1925)〔22歳〕

1月12日、映画『水兵の母』(監督小笠原明峰)の完成試写会と披露宴が、上野精養軒で開催される。
東郷平八郎、農相高橋是清、逓相犬養毅、海軍大将米内光正、床次竹二郎ら政界、軍の要人が来賓として招かれた。
1月19日、皇太子殿下(現天皇)、妃殿下が、同映画を台覧される。
2月9日、大正天皇が、静養先の葉山御用邸で天覧される。
3月5日、『水兵の母』、神戸キネマ倶楽部ほか全国各地で公開。50本のフィルムが作製され、うち13本が全国を巡回、国民的話題となる。
『水兵の母』が大ヒットし、小笠原プロダクションを一躍有名にする。そして、女性シナリオライター第一号として、新聞社の取材が殺到する。日本女子大学では映画見物でさえ禁止されており、退学を恐れ、卒業まで待って欲しいと懇願する。
同月、日本女子大学を卒業。
この頃、『サンデー毎日』に、写真付きで紹介される。(写真)
4月、「東洋のハリウッド」松竹キネマ蒲田撮影所の脚本部に入る。
10月、特作映画社設立。あやめが学生時代に書いたシナリオ『極楽島の女王』を第一作として映画化すると発表。主演は高島愛子。内田吐夢、栗原トーマスらが出演。撮影を、ヘンリー小谷、碧川道夫が担当した。
12月26日、冒険活劇『極楽島の女王』(監督小笠原明峰)が帝国劇場で公開される。
12月27日、城戸四郎の指導のもとで書いたあやめ原作『お坊ちゃん』が、人気スター・諸口十九の帰朝第一回主演映画の脚本募集に応募3000作品の一等に当選、映画化されることになる。
大正15〔昭和元〕年(1926)〔23歳〕

1月24日、この日発行の『蒲田週報』に、あやめの蒲田撮影所脚本部への正式入社が発表される。
また、同誌に『お坊ちゃん』製作に関する第一報が載る。以後、城戸所長の総指揮のもと、蒲田所属の若手俳優のオール・スター・キャスティングで製作される方針が打ち出され、その製作過程が『蒲田週報』はじめ各映画雑誌に逐次紹介。映画ファンの関心と期待を高めた。
1月25日、『お坊ちゃん』の第一回本読みが行われる。監督島津保次郎、出演者諸口十九、藤野秀夫、英百合子、松井千枝子らが出席。
5月1日、『お坊ちゃん』(監督島津保次郎)、浅草電気館にて封切。大好評を博し、3週続映となる。
5月4日午後1時より、東京八大学映画研究会主催による「お坊ちゃん鑑賞会」がカフェー聚楽にて開催。二十数名が出席し、高い評価を受ける。
また、『映画時代』(文芸春秋社)の7月創刊号で、日活の『日輪』とともに『お坊ちゃん』が合評され、その様子が紹介される。
5月23日、『母よ恋し』(監督五所平之助)が、浅草電気館にて封切。あやめにとって、はじめての原作・脚本作品。母と娘の再会と別れを描いた母ものの新派調悲劇で、主演をつとめた名子役高尾光子の可憐な演技が観客の涙をさそい大当たりする。こののち、高尾光子とのコンビの「お涙頂戴もの」を、数多く書かされるようになる。
7月、雑誌『芝居とキネマ』で、女性シナリオライターの先駆者として、日活の林義子とともに写真付きで紹介される。
同月、雑誌『映画時代』七月号に、同誌創刊記念の映画脚本懸賞募集記事が載り、あやめは<荻野夢子>のペンネームで、『久遠の華』を応募する。
9月5日、蒲田撮影所で大規模の組織改編が行われ、あやめは城戸所長の直属となる。
9月21日、あやめ原作『いとしの我が子』(脚本・監督五所平之助)が、浅草松竹館にて封切。
この頃、蒲田映画村の一角、矢口町下丸子五二七番地に移り住む。
11月6日、少女悲劇『曲馬団の少女』(監督鈴木重吉・斎藤寅次郎)が、浅草松竹館にて封切。
12月1日、『愚かなる母』(監督池田義信)が、浅草松竹館にて封切。
昭和2年(2927)〔24歳〕

1月5日、初めての恋愛喜劇『恋愛混戦』(監督島津保次郎)が、浅草電気館で公開される。
5月、雑誌『映画時代』創刊記念脚本募集に、<荻野夢子>のペンネームで応募した脚本『久遠の華』が当選する。賞金二千円。日活での映画化が約束された。
7月、この月発行の雑誌『料理の友』(大日本料理研究会)で、少女小説「目無千鳥」の連載が始まる。
8月26日、時代もの『木曽心中』(監督吉野二郎)が、浅草電気館で公開。
9月、雑誌『映画時代』誌上で、<荻野夢子>が松竹蒲田脚本部所属の<水島あやめ>だったと発表。
9月30日、少女哀話『孤児』(監督大久保忠素)、浅草電気館で公開。原作脚本水島あやめ、監督大久保忠素、主演高尾光子のトリオで製作された少女ものの第一作。以後、「オタミ・トリオ」と呼ばれ、人気を博す。
10月17日、あやめの帰省を機に、長岡高等女学校のクラス会が長岡市で催される。人気女性シナリオライターの来訪を聞きつけて、新潟市から母娘が弟子入りのお願いに来る。
12月15日、少女悲劇『天使の罪』(監督大久保忠素)、浅草電気館で公開。
昭和3年(1928)〔25歳〕
.jpg)
1月1日、この日発行の日本女子大学機関紙『家庭週報』に、一面を裂いて、あやめの実績と近況を掲載。「私達桜楓会員の非常な喜び」と紹介される。
2月18日、新派悲劇『故郷の空』(監督大久保忠素)が、浅草電気館で公開。
5月25日、社会悲劇『鉄の処女』(監督大久保忠素)が、浅草電気館にて公開。
6月8日、少女悲劇『神への道』(監督五所平之助)が、浅草電気館にて公開。
7月7日、吉屋信子の小説を原作とした文芸作品『空の彼方へ』(監督蔦見丈夫)が、浅草電気館にて公開。『地の果てまで』『海の極みまで』の人気三部作の一編を映画化したもの。
7月29日、この日付で、故郷の母方の祖父宛に、母に代わって近況を知らせる手紙を送る。文面から、経済的に、かなり余裕ができていたことがわかる。
8月17日、喜劇『妻君廃業』(監督大久保忠素)が、浅草電気館にて公開。
9月14日、「オタミ・トリオ」第四弾『をとめ心』(監督大久保忠素)が、浅草電気館にて公開。
12月30日、『美しき朋輩たち』(監督清水宏)が、浅草電気館にて公開。「涙あり笑いあり、少年少女の純情なる心境を描きたる児童映画の好範とも言わるべき作品」(『蒲田週報』)と紹介される。
昭和4年(1929)〔26歳〕
.jpg)
5月25日、『明け行く空』(監督斎藤寅次郎)が、浅草帝国館にて公開。雑誌『少女の友』に連載された新井睦子の少女小説の映画化。フィルムはほぼ完全な形で現存し、挿入歌の楽譜も見つかっている。斎藤寅次郎、二十三歳のときの監督作品で、あやめの生真面目さと斎藤の喜劇性が程よくミックスした佳作であった。
8月1日、簡易保険の宣伝作品『親』(監督清水宏)が、浅草帝国館にて公開。
この頃から、松竹でトーキー化への模索が始まる。
昭和5年(1930)〔27歳〕
.jpg)
2月1日、喜劇『現代奥様気質』(監督重宗務)が、浅草帝国館にて公開。
2月14日、教育映画『純情』(監督成瀬巳喜男)が、浅草帝国館にて公開。
10月28日、父団之助(隆雅)、東京下谷車坂の寓居で死去。享年68歳。
7月20日、風刺劇『モダン奥様』(監督重宗務)が、浅草帝国館にて公開。
昭和6年(1931)〔28歳〕
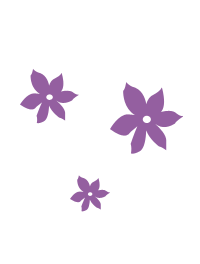
2月22日、母もの『美しき愛』(監督西尾佳雄)が、浅草松竹館にて公開。
6月19日、吉屋信子の小説の映画化第二弾『暴風雨の薔薇』(監督野村芳亭)が、浅草帝国館にて公開される。
この年公開された『マダムと女房』(監督五所平之助)で、日本映画のトーキー化が本格化する。映画の有声化は、脚本家にとっても大きな変化をもたらし、あやめはシナリオ手法に苦労する。
一方、観客の嗜好にも変化が起こり、会社から「もっと色っぽいものを書いて」と言われ、思い悩んだすえ、「私にはできません」と答えたという。
昭和7年(1932)〔29歳〕
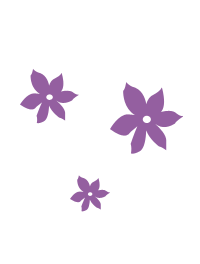
3月10日、『青空に泣く』(監督成瀬巳喜男)が、浅草松竹館にて公開。
8月12日、『輝け日本の女性』(監督野村浩将)が、浅草帝国館他で公開。野田高梧との共同脚本。ロサンゼルス・オリンピックを舞台にした作品で、主演は田中絹代だった。
昭和8年(1933)〔30歳〕

10月12日、吉屋信子の小説映画化第三弾『女人哀楽』(監督佐々木恒次郎)が、浅草帝国館で公開。
昭和10年(1935))〔32歳〕

1月27日、『接吻十字路』(監督佐々木恒次郎)が、浅草帝国館にて公開。
5月24日、『輝け少年日本』(監督佐々木恒次郎・佐々木康)が、浅草帝国館で公開。皇太子殿下(現天皇)降誕奉祝記念映画。あやめの映画作品のなかで唯一のトーキーである。
この年、松竹は撮影所を大船に移転することを決定。それを機に、蒲田撮影所脚本部を退社。少女時代からの夢だった小説家に転身する。